
研修会編第4弾となります。ディープな内容が続きますがお付き合いくださいませ。因みに人格の虐待という言葉は聞いたことありますか?今回は「人格への虐待」というテーマについて研修で学んだことそこから自分自身への落としこみをしてまいりたいと思います。
-
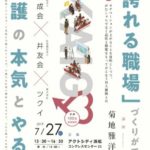
-
「誇れる職場づくりができる介護の本気とやる気」研修会に参加してのまとめ
浜松市で菊地雅洋先生を招いての研修会がありましたので参加してまいりました。久しぶりの研修会でありましたのでせっかく聞いたこと、学んだことをシェアが出来ればと思い、今回はこの研修会についてのまとめをかい ...
続きを見る
人格への虐待【誇れる職場づくりができる研修会より】

講義を聞く限りでは精神的虐待に近いとは思いました。そもそも精神的虐待は無視をしたり大声で脅したり、拒否的な態度をとることをいいますが、この人格への虐待は精神的な虐待も包括しているイメージで差し支えないかと思います。いわゆる、【一人の人としての有るべき姿を拒絶する】ことではないでしょうか?
そして研修の中では人格への虐待に関しては「羞恥心」という部分にフォーカスをして話をされておりました。
研修の内容について

羞恥心に配慮がないことも虐待と言えるのではないか
好む好まざるにかかわらず、自分の恥ずかしい部分、人に見られたくない部分も含めて支援が必要になる状態だとしたら、あなたは介助者に何を求めますか。
人格を捨てなければ支援を受けられないとしたら、あなたはどうしますか?
これらが無視されることは「人の暮らし」として普通ではない状態を生む
とのことでした。
羞恥心というものは誰にでもあります。勿論個人個人によって感覚の差はあるかと思いますが、他人に見られたくない部分(身体的にも精神的にも)は必ずあります。こういった部分も配慮出来なければ適切なケアとは言えないのかもしれません。
人格の虐待事例

ここからは講義の内容と個人的見解も含みながら書いてまいります。
前述の「当たり前で行われる週2回の入浴は当たり前?【誇れる職場づくりができる研修会より】」でイラストを、のせたのですが、カーテン仕切りの無いなかでのポータブルトイレ介助、当時「⚪⚪さんは認知症だから大丈夫」といった、会話がされていたようです。また他の例だと入浴介助の際に外介助の方が直ぐ入浴が出来るように、まず服をさっさと脱がせて待機させる、なんていうこともあったようです。
人格への虐待の特徴

高齢者への虐待はとりわけ、身体のイメージが強いかと思います。ですので介護者と利用者の関係となりますが、この人格への虐待は介護者と利用者との一対一の関係は勿論のこと、介護者と介護者同士で利用者のいない部分でも起こり得るというのが特徴的になります。「⚪⚪さんって (認知症が) 進んでるからこうでいいよね」といった会話が為されているのもわかりやすく言えば人格への虐待ということでイメージをしていただければわかりやすいかと思います。
人格への虐待の防ぐ為には

まずは 「感覚の麻痺」 に気を付けること、そして「他人の目の意識」を持つことではないでしょうか。
「感覚の麻痺」 に気を付けること とは
しーちゃん@介護予防運動指導員@jiyon_cがコメントでも下さっていたのですが、虐待が起こるのは入所系の施設ばかりの印象があります。(もし何かデータをお持ちの方がいればぜひご提供くださいま)やはり閉鎖的な空間で創り上げられる都合のよい人間関係の慣れが悪い方向に進んだ結果「感覚の麻痺に」繋がるのではないでしょうか?
「他人の目の意識」を持つこと とは

「ご利用者のご家族が横にいる」ということを常に考えることです。
個人的にはこの考え方は全ての虐待を防ぐのに効果的ではないのかな?と思っております。まあただ、実際のところは常にそういう意識を持つというのも難しいですし、それを四六時中監視しているわけにはいかないので理想なのかもしれません。
いかなる場合でも「虐待はあってはならない」

これに尽きます。ただ思考停止はNGです。虐待の起きた背景、関係性、状況はしっかりと考えなければなりません。
私たちは医療・福祉のスペシャリストなのです。いかなる場合でも虐待はあってはなりません。
最後に
今回は人格への虐待から派生して虐待についても少し述べた内容となりました。ただ正直な話自分が現場時代の時感情的になりそうな時もありました。また常に指導をした職員さんには「怒れることがあるのは当然。怒るという感情をもってはいけないということはないですよ」ということを常にお伝えさせて頂いておりました。実際何が正解かはわかりません。ただ虐待がなくなることをあきらめずに考えていきたいものです。
「誇れる職場づくりができる介護の本気とやる気」研修会に参加してのまとめ